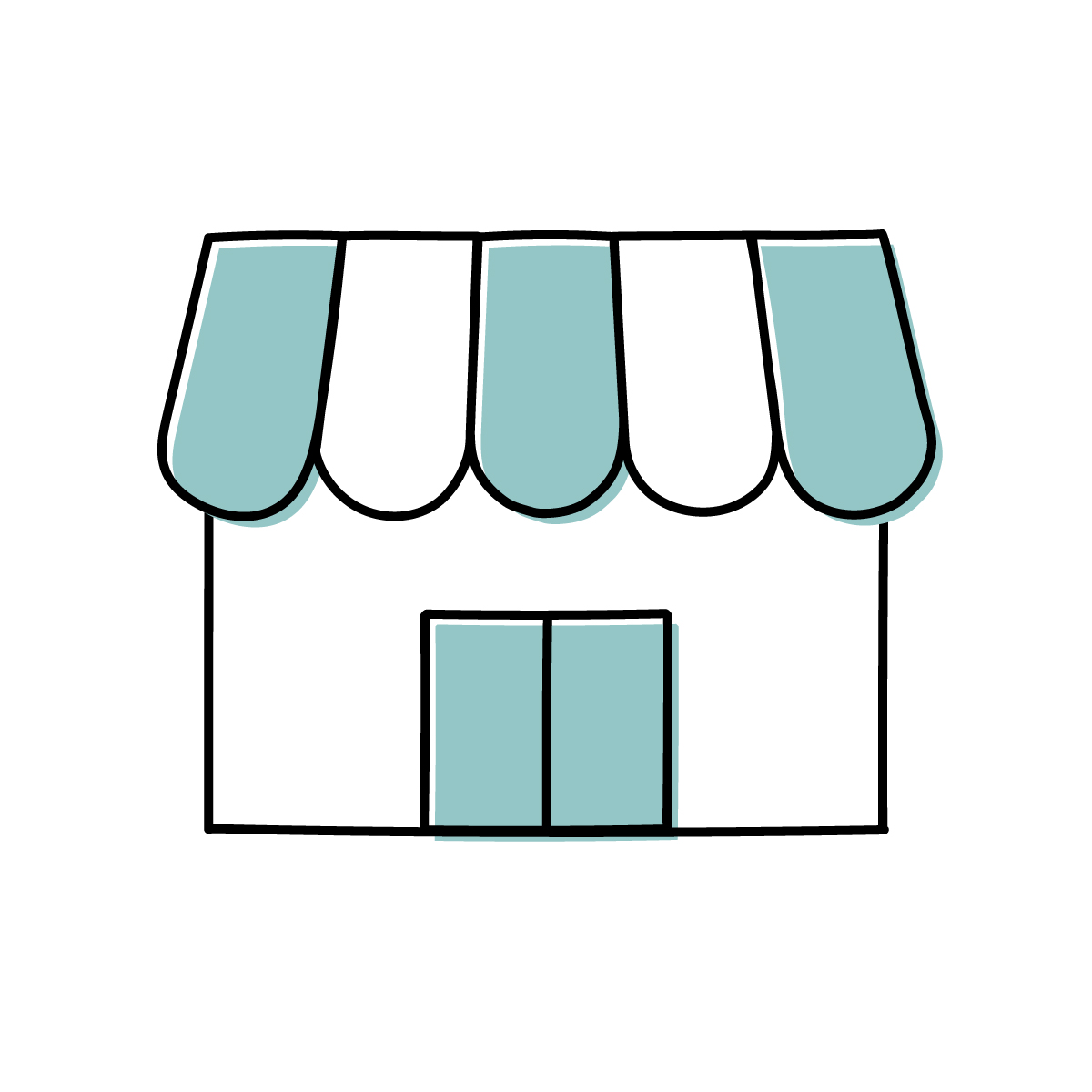今回のお話しは専門家はいつも、2社つかうべしの後編になります。
気になる方は、ぜひ覗いて行って下さいね。
竹ちゃんよ、前回の話しで専門家を2社以上使った方がいい理由は分かったんだけどよ、正直そんなに予算なんかねぇんだ。それと、どうやったら「いい専門家」を選ぶ物差しなんてのも持てるんだよ。
それは多くの中小零細事業者が抱える悩みですね。確かに、専門家を選ぶ基準がなかったり、予算的に余裕がない場合にはハードルが高く感じられることもあります。でも「2社以上」を想定して工夫することで、その問題を解決できますよ。それに物差しやステージの考え方を取り入れると、さらに効果的です。
1. 物差しを持つために2社使う
たっつぁん、専門家を評価するためには比較するための「物差し」を持つことが重要です。ただほとんどの中小零細事業者は、自分たちだけでその物差しを持つのが難しいんですよね。特にデジタルや広告の分野では、専門用語を並べられると「これがベストなんだろう」と信じるしかなくなることが多いです。
おぉ、それはまさにオレのことだな。やれ「インプレッション数がどうだ」とか言われても、こっちはチンプンカンプンで、結局「任せるしかねぇな」ってなっちまうんだよ。
そうなんです。だからこそ、2社以上の専門家に同じ課題について相談するんです。それぞれの提案を比較することで、たっつぁん自身の中に「こういう提案が自分のビジネスに合っているんだな」という基準が生まれてきます。そして、それを繰り返すことで、少しずつ自分の物差しを持てるようになりますよ。
2.限られた予算で2社体制を実現する方法
たっつぁん、予算が限られている場合でも2社以上を使う仕組みを作ることは可能です。大事なのは「メイン業者」と「スポット業者」に役割を分けることと、「期間を限定する」ことです。
具体的にはどうすりゃいいんだ?オレみてぇな工房でもできるのか?
例えば、月に10万円の予算があるとしたら
• メイン業者:8万円で日常的なSNS運用や広告配信を担当。継続的な作業を請け負う。
• スポット業者:2万円で季節ごとのキャンペーンや、新しい戦略の提案をお願いする。
さらに最初の3か月間だけ2社体制で運用してみて、どちらがより自分の工房に合っているかを見極めることもできます。この期間をテストとして活用すれば、無駄を抑えながら効果を最大化できますよ。
なるほどな。3か月なら試しにやってみる余裕はありそうだし、それで物差しを作れるってわけだな。
3. 物差しを作りながらステージに合わせた判断をする
たっつぁん、2社を使うことで「自分の工房に必要な提案が何か」を見極める目が養われます。それと同時に、自分のビジネスが今どのステージにいるのかを意識することも大事です。
ステージってのは、さっき言った「地元密着」とか「全国展開」とか、そういう段階のことだよな?
その通りです。例えば、たっつぁんが「新しい顧客を開拓したい」というフェーズにいるなら、それに強い専門家を使うべきですし、「既存の顧客をもっと深くつなぎ止めたい」というフェーズなら、それに特化した提案をしてくれる専門家を選ぶべきです。
なるほどな。ステージを意識しねぇと、どんなにいい専門家でも合わなくなることがあるってわけか。
その通りです。ステージに合わない専門家を使うとせっかくの提案が生かされず、無駄なコストがかかってしまいます。それを避けるためにも、2社を活用して適切なステージに合った提案を見極めることが大事なんです。
結論:物差しとステージを意識して2社体制を活用しよう
まとめると、2社以上を活用することで物差しを作り、ステージに合わせた判断ができるようになります。そして予算が限られている場合でも、メインとスポットの役割分担や期間限定の試験運用を取り入れることで、無理なく2社体制を実現できます。
よし、竹ちゃん。それならオレも試してみる気になったぜ。まずは3か月、2社でやってみて物差しを作ることから始めてみるよ。また相談に乗ってくれよな!
もちろんです!たっつぁんの伝統工芸をさらに広めるために、全力でサポートしますよ!
たっつぁん、どんどんデジタルマーケティングに強くなっていますね!
皆さんも、ぜひ専門家の1社に最人最を検討してみてはいかかでしょうか。